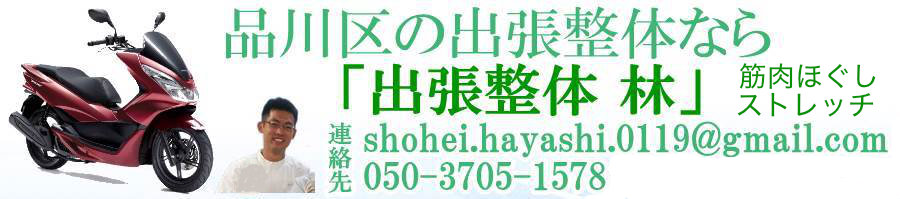コード進行分析方法 超初級
2020/08/28
久しぶりに、音楽系の備忘録を記載します。
コード進行を分析していく際の手順です。
1.調の判定
2.ダイアトニックコードを見つける
3.ノンダイアトニックコードを解釈する
この順番で見ていきます。
具体的にはどうするか。
1.調の判定
このページを見ちゃいましょうw
https://matome.naver.jp/odai/2136511911915125501
まずは楽譜の臨時記号の数を確認し、上記のHPで、どの調か判定します。
すると、2つまでに絞れます。
例えば♭1つなら
ヘ長調(F Major) または ニ短調(D Minor)
といった具合です。
調の確定は最初か最後のコードでOK
どちらかを確定させるのは、だいたい最初か最後のコードがFかDmになってるので、それで該当する方にしましょう。
それでダメなら難易度高くなるので今は無視でw
もしそれでダメなら、全体的に判断しなければいけないので、ここではスルー。
一応、いかに書いてあるようですが、ちょっと難しすぎるのでパスw
http://楽典.com/gakuten/chohantei.html
2.ダイアトニックコードを見つける
このページでカンニングしろ
これは1.調の判定 ができているのならば簡単です。
その調のダイアトニックコードのページを見ましょうw
http://music.cyberlab.info/diatonicChord/
さきほどのDmだと仮にするなら、こちらのページということになります。
http://music.cyberlab.info/diatonicChord/naturalMinor/D.html
ここのページに書いてあることが読めないとういことでは、少し基礎知識の勉強が足りないと言えるでしょう。別途勉強が必要になります。
ダイアトニックコードを色付けしよう
ここででてくるダイアトニックコードを楽譜上でまずは色つけたりしましょう。
3.ノンダイアトニックコードを解釈する
ダイアトニックコードの進行は気にすんな
音楽理論?と呼んでいいのかわかりませんが、私がここまで習ったコード進行の知識として、
「ダイアトニックコードはどういう順番で置かれてても、問題ない」
というものがあります。
もちろん、トニックとかドミナントとかありますが、結局進行を分析していくと、トニック→トニック とか ドミナント→トニック が普通の所を、ドミナント→サブドミナント とか、正直、役割名をつけてる意味があるのか?という進行ばかりです。
なので、ダイアトニックコードはどういう順番で置かれてても、問題ない ということで、コード進行の解釈をするのは辞めるべきだという解釈に至りました。
なのでやるべきはノンダイアトニック探し
ということは、やるべきことは残りのノンダイアトニックコードです。
ノンダイアトニックコードを分析すればいいだけなので、色をつけなかった部分を見ていきます。
やること
1.ノンダイアトニックコード(イ)の次のコード(ロ)を見る
例) keyがDmの曲で以下の進行の場所があったとする
C(Ⅶ) → G7(Ⅳ7) → Csus4(Ⅶsus4) → C(Ⅶ)
青がダイアトニックコード、赤の箇所がノンダイアトニックコードだとすると赤G7(Ⅳ7)が登場したので、その次のコードを見る。
Csus4(Ⅶsus4)
である。
2.(ロ)がダイアトニックコードなら、(イ)→(ロ)の間にドミナントモーションが成り立っていないかチェックする。
例)ダイアトニックコードじゃなくて、ノンダイアトニックコードだった。(Csus4だった)だが、sus4コードはよくあるパターンらしく、下記3の手順に移る
3.(ロ)が sus4 コードで、(ロ)Csus4→(ハ)C みたいなルート音が同じで進行する場合は、(ロ)のsus4は(ハ)の装飾コード的な役割なので考えずに、(ロ)→(ハ)にドミナントモーションが成り立ってないかチェックする
例)Csus4コードの次がCだったので、このコードはCを盛り上げるために、ちょっと変えたバージョンとして入れられたに過ぎないつながりと考えるらしい。
ということは、実質はこういう塊で捉える
C(Ⅶ) → G7(Ⅳ7) → Csus4(Ⅶsus4) → C(Ⅶ)
ここで、再び、2.に戻る。
この2つの間にドミナントモーションが入っているかどうかを考えるのだ。
Cをトニックとした場合のG7はドミナント。
G7(Ⅴ)→C(Ⅰ) というドミナントモーションが成り立っている。
が、今回は調がDmということなので、セカンダリードミナントであると言える。
結論
←----セカンダリードミナント-----→
C(Ⅶ) → G7(Ⅳ7) → Csus4(Ⅶsus4) → C(Ⅶ)
という風に解釈するということである。
やるべき作業内容
つまり、最初に戻るが、
- 調の判定
- ダイアトニックコードを見つける
- ノンダイアトニックコードを解釈する
- ドミナントモーションが存在するかどうか考える
- 通常のドミナントモーション
- セカンダリードミナント
- ドミナントモーションが存在するかどうか考える
ということで、コード進行分析でとりあえずやることはここまでは定型作業ということでOKと思われる。
今後の課題
じゃあ、セカンダリードミナントじゃなかったらどうするのか?
ノンダイアトニックコードが何個も連続したらどうするのか?
は、今後の勉強課題という感じである。(わかり次第更新します)
ほとんどドミナントモーションだったのを実感
実際のある曲をやって見たら、構成のほとんどがこのパターンだった。
そのため、まずはこの定型分析作業をこなしていけば、曲の8割くらいは分析できたことになると思われる。
あると理解の助けになる知識
尚作業の際に、以下の認識でやるとすんなり理解できた
- ノンダイアトニックコードがダイアトニックコードの間に入った場合、ダイアトニックコードは次に出てくるダイアトニックコードと繋がっていると考える。
- そのため、ノンダイアトニックコードは次のダイアトニックコードを装飾するために存在しているから、前のダイアトニックコードとのつながりを考える必要はない
┌────────────────┐
│ ↓
C(Ⅶ) → G7(Ⅳ7) → Csus4(Ⅶsus4) → C(Ⅶ)
└────装飾────────┘
こういうつながり
という風に解釈するということである。
そうじゃないと C → G7は一体何の理論的つながりなんだと考えが止まらない。
C は次のダイアトニックC と繋がっているが、その間を装飾してあるだけ と考えると割と腑に落ちた。
他豆知識箇条書き
あとは豆知識的な感じで覚えておくこととして
- sus4コードは普通のコードに解決したがる装飾的な使い方が多い。(そのため、その使い方の場合は装飾扱いで無視して良さげ)
- ドミナントモーションは7コードからトニックへの解決であり、m7コードから解決しても、ドミナントモーションとは呼ばない(解決してる感じはするらしい)
- C7sus4→Fみたいなのは、sus4ついてるけど、C7が残ってるからドミナントモーションと呼んでOK
- マイナーキーの場合は、ドミナントモーション作るために、Ⅴのコードをダイアトニックから外して、いきなり普通の7コードで使うことが普通にある
らしい。
とりあえず、今日の発見?はここまで。
読んでいただきありがとうございました。
興味はあるんだけど
- 失敗したくないから一度試したい
- 家に人を呼ぶってのがイメージできないから、お試ししたい
- 施術の圧加減などが自分に合うか、リスクを減らして試してみたい
という、新規の方向けに、40分6,000円でお試し施術しています。
(通常30分6000円にお試し用で10分追加プレゼント)
期間限定なので、お早めに。
下記お試し専用Lineより、ご連絡くださいませ。
Lineに登録すると、他にも事前予約割引や、お得なスタンプカードも得られます。
ご登録して損はありませんよ。
詳しい情報として下記もご参考になさってください。
こんな時にもお役に立てます。
- 【メンタル疲れ】愚痴を聞いてくれる整体
- 【夜遅く受けたい】夜遅く(深夜)でも受けられる月一出張整体!
- 【家に来て欲しい】家から出るのがめんどくさい
- 【気分が落ち込んでいる】メンタルがネガティブになったら整体をうけるべし
- 【肩が疲れた】重いバックを長時間肩にかけたので肩こりが
- 【足のむくみ】リモートワークで歩かなくて足を動かしてないのでだるい
- 【介護疲れ】介護職で腕が疲れた
- 【考え過ぎ疲れ】勉強しすぎて頭が疲れた
- 【PC使いすぎ疲れ】タイピングのしすぎで指が疲れた
- 【仕事しすぎ疲れ】残業が多く姿勢が悪くなってきた
- 【コロナ禍疲れ】マスクしすぎてなんか少し息苦しい
- 【コロナ禍疲れ】ヘッドホンやマスクで耳が疲れた
メニュー
サブメニュー