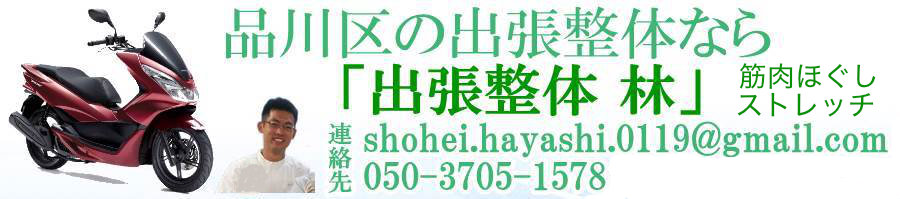コード進行分析方法 超初級 その2
2020/08/28
前回、コード進行の分析として、以下を学びました。
- 調の判定
- ダイアトニックコードを見つける
- ノンダイアトニックコードを解釈する
- ドミナントモーションが存在するかどうか考える
- 通常のドミナントモーション
- セカンダリードミナント
- ドミナントモーションが存在するかどうか考える
今回は、さらに進んで考えます。
- ノンダイアトニックコードを解釈する
- ドミナントモーションが存在するかどうか考える
- 通常のドミナントモーション
- セカンダリードミナント
- 関係するノンダイアトニックコードか考える
- 借用コード
- 裏コード
- コーダルのアプローチ
- クロマチックアプローチ
- フリジアンアプローチ
- 3度の移動
- ドミナントモーションが存在するかどうか考える
今回はこちら、赤字の部分を取り上げていきます!
場面としては、ドミナントモーションではなかった。
じゃあ、このコードはなんで存在してるの?
って時の可能性として、次に該当するか考えます。
借用コード=同主調・平行調のコードを使うこと
やっぱり、いくら音楽が自由といえど、なんでもかんでも使うとめちゃめちゃになるわけです。
そこで、何かしら関係のあるコードが使われることが多い。
それがこれ。借用コード。
同主調もしくは、平行調のコードを使うという物です。
同主調はkey C なら Cm
平行調はkey C なら Am
のコードを持ってくるというものです。
これは理解しやすいかな。同主調はルート音が一緒だからいけるでしょ と。
平行調は、使ってるスケールの音が同じだからいけるでしょ ですね。
サブドミナントマイナー
ちなみに、似た考えで「サブドミナントマイナー」があります。
これは、4番目のダイアトニックコード(をサブドミナントの役割のコードと呼ぶのですが)は、どのメジャーキーにおいても常にメジャーキーなのですが、ここにマイナーキーを持ってきても大丈夫という理論らしいです。
しかし、このサブドミナントマイナーは、結果的に常に、そのメジャーキーに対する同主調の4番目のコード(=サブドミナント)となります。
例えば、Aメジャーキーの4番目はDで、Aマイナーキーの4番目はDmです。
なので、同主調のコードを借りることは借用コードと表現すると上で調べました。なので、サブドミナントマイナーは借用コードのうちの限定された使い方を表す用語であると言う風に、捉えております。
裏コード=Ⅱ♭7のこと
Ⅴの音がⅠに向かう性質がある という理論がドミナントモーションでした。
そのドミナントモーションがどうしてそういう性質があるかといえば、トライトーン(三全音)と呼ばれる音程で構成されているかららしいです。
トライトーンだと不安定な感じがするので、安定にいかないと人間気持ち悪い。
だからⅤ(気持ち悪い)→Ⅰ(気持ち良い)となりがちだと。
そのトライトーンを他にも持っているのがⅡ♭7
key C で言えば D♭7 らしいのです。
え?、各12の調で、Ⅴに相当する音があるんだから、もっとあるんじゃないの?と思いましたが、ここは、やはり繋がりがないとめちゃくちゃに聞こえるってことですよね。
ここでの繋がりは、このⅡ♭7はⅤの音に構成音が似ている のに、トライトーンを持っている という所のようです。
実際、key C で言えば D♭7 とG7を比べてみると
D♭7=レ♭・ファ・ラ♭・シ
G7 =ソ・シ・レ・ファ
とまあ、2つ一緒。2つを多いとみるか、少ないとみるかは・・・他のトライトーンコード全部見て比較するのは面倒なので、やめときますが、きっと2つ構成音が一緒というのは、あまりないことなのでしょうw
五度圏と呼ばれるコードの循環表みたいなのがあるのですが、その表の上で見ると、ちょうど裏に位置する場所にある関係らしく、裏コードと呼ばれる所以らしいです。
よって、Ⅴの音と似ているので、Ⅴの代わりに使われるⅡ♭7→Ⅰというのがあるようです。次が1で、ダイアトニック外のコードが来てたら、ちょっと疑ってみるのが良さそうです。
コーダルのプローチ
Chordal (コーダル)というのは、「和音の」という意味がある英単語です。
なんでもコーダルなアプローチとモーダルなアプローチというのがあるらしくて、あまりよくわかりませんでしたが、ざっくりいうと、「コード適当に引いて気持ち良ければOK」みたいな感じらしいです。
なので、コードがたくさんあって、あんまり進行上の繋がりが不明だなーと思ったら、とりあえず、コーダルなプローチってことにしておくという逃げですね(笑)
ジャズのコードトーン重視のアドリブをする際に使われる概念だそうな。
クロマチック アプローチ
クロマチックというのは半音のことですね。
半音で接している進行をしていれば、とりあえず、クロマチックアプローチなんだなと思うということみたいです。
例えば、key Gm で Gm→A♭ と出てきたと。
ディグリーコードネームで言えば、Ⅰ→Ⅱ♭ で、ダイアトニックではない。
Ⅱ♭7→Ⅰってわけなら、裏コードだけど、7でもないし、次のコードがD♭だった。
そうすると、まあとりあえず、Gm→A♭は半音となりで動いてるからクロマチックアプローチってことにしとこうと(笑)
そんな感じでしょうか。
大前提として、一つのコード進行には複数の考え方が当てはめられるらしく、そういう風にも捉えられるし、こういう風にも捉えられるってことがあるみたいなので、困った時のクロマチック・アプローチってことにしておきましょうw
フリジアンアプローチ
フリジアンスケールという、スケールがあるらしく、そこ1小節だけみてみたら、そのスケールの音で構成されてた(だけど、もとの調のダイアトニックではない)みたいな時、こう考える
Phrygian=フリギア王国[人・語・風]の
なので、そういう王国でよく使われていた音なのかな?
半音・全音・全音・全音・半音・全音・全音
という並びらしい。
よくある 短3度の移動
これは、理論ではなくて、よくあるパターンという理解で進むと良いようだ。
つまり、理論外ではあるが、実際よく使われてるということで、スルーみたいな。
実際こういう信仰があった
Cm→E♭m
キーはGmなので、ディグリーで言うと
Ⅳ(4)→Ⅵ(6)
相当の動きではあるものの、E♭m なので、もし、ダイアトニックならE♭になるはずなので、違う。
借用コードならEmとなり、E♭ mではないため、違う。
と言うような時。
C→E♭は ド→ド#→レ→レ#(=ミ♭)という3つ分半音動いている。
これを短3度という。
この幅、短3度のベース音のコードの移動はよくあることらしい。
なので、そういうのを見つけて他で説明できない場合「ああ、短3度の移動ね」
という解釈で乗り切るらしいw
感想
自分でノンダイアトニックで適当に音配置すると不快な音にしかならないのに、そうでないものが多々あると、こういうの勉強すると思う。
やはり、なんらかの繋がりというのがあれば、ダイアトニックでなくても、快適な音になるのだろうな と感じた。
また、先人は、色々試して気持ちよかった音を説明する際に、こういう関係性があるんだよと、うまいこと説明してきたんだなということだなと思った。
読んでいただきありがとうございました。
興味はあるんだけど
- 失敗したくないから一度試したい
- 家に人を呼ぶってのがイメージできないから、お試ししたい
- 施術の圧加減などが自分に合うか、リスクを減らして試してみたい
という、新規の方向けに、40分6,000円でお試し施術しています。
(通常30分6000円にお試し用で10分追加プレゼント)
期間限定なので、お早めに。
下記お試し専用Lineより、ご連絡くださいませ。
Lineに登録すると、他にも事前予約割引や、お得なスタンプカードも得られます。
ご登録して損はありませんよ。
詳しい情報として下記もご参考になさってください。
こんな時にもお役に立てます。
- 【メンタル疲れ】愚痴を聞いてくれる整体
- 【夜遅く受けたい】夜遅く(深夜)でも受けられる月一出張整体!
- 【家に来て欲しい】家から出るのがめんどくさい
- 【気分が落ち込んでいる】メンタルがネガティブになったら整体をうけるべし
- 【肩が疲れた】重いバックを長時間肩にかけたので肩こりが
- 【足のむくみ】リモートワークで歩かなくて足を動かしてないのでだるい
- 【介護疲れ】介護職で腕が疲れた
- 【考え過ぎ疲れ】勉強しすぎて頭が疲れた
- 【PC使いすぎ疲れ】タイピングのしすぎで指が疲れた
- 【仕事しすぎ疲れ】残業が多く姿勢が悪くなってきた
- 【コロナ禍疲れ】マスクしすぎてなんか少し息苦しい
- 【コロナ禍疲れ】ヘッドホンやマスクで耳が疲れた
メニュー
サブメニュー