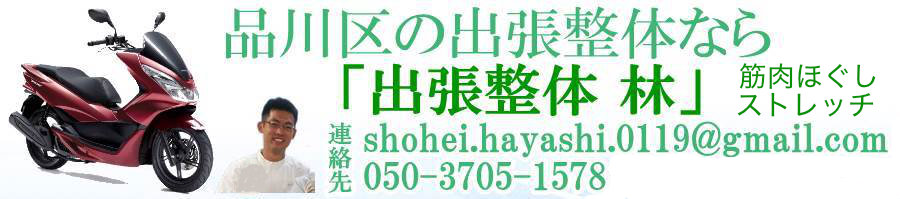冷やすと痛みが和らぐ理由
2016/07/05

腰痛の人間
きっかけ:昨日から腰が痛い
昨日からやたらと腰が痛く、歩くのすらしんどい感じになりました。
私は、整体師なので、自分で少しでも軽減しようと色々試みましたが、あまりしっくりくることができず、不甲斐なさを感じます。
炎症かと感じた
患部が熱っぽく、痛みが起きているので、最終的には「冷やす」という選択をとりました。
(炎症部位には冷やすというのが基本で、そういう箇所にほぐしなどを行うと逆に悪くなると言われています。)
こういう箇所には整体の技術ではどうしようもならないと私は思います。
(東洋医学の針治療などの人はまた違う考えになるかと思いますが。)
救急マニュアルRICE

救急のマニュアルではRICEという言葉でそれが一般的に語られています。
詳しくはこちらに良く載ってました。
ケガを最小限にくいとめる→つまり出血や腫れを止めるために最も有効な方法は冷やすことです。
しかし、前から疑問に思っていたのですが、なぜ冷やすと良いのでしょうか?
(冷やすのがどうして有効なのか?という意味です。)
捻挫、肉離れ、靱帯の損傷、打撲、骨折、脱きゅうなど、たいがいのケガの場合は内出血と腫れが起こります。
この内出血と腫れを最小限にくいとめる(=組織の再生を促し、回復速度を速める)ために、一番有効なのが冷却(アイシング)、
つまり患部を氷などで冷やすことです。
つまり、組織の再生を促し、回復速度を速めるのに有効だから
というのが理屈です。
でも、どうしてそれが冷やすなのかが知りたいのです。
この機会にWikipediaで調べてみた
Wikipedia アイシング(治療)に載ってそうだったので読んでみました。
しかし、読んでもらえばわかると思いますが、正直 日本語の表現が難しい。。。
でも頑張って私なりに、解釈してみました。
結論は 血行を抑えるためにやる ということ
一番、Wikipediaに載っていた表現でわかりやすかったのはこれです。
アイシングは血行を抑えるための行為である。
これを読んで、全てはそのためにやってるんだなというイメージが結構できてきました。
これを踏まえたうえで林的に解釈するとこんな感じでしょうか。
林的解釈

(1)血を止める効果
となれば、まずは「血行を良くする」よりは「血を止める」方が大事だろう。
冷たいところの周辺の血液の量は低下するらしい。
炎症が起きているとは、おそらくこれの小さい版が起きていると考えればわかりやすいのではないか?(と想像した)
(2)新陳代謝を上げる効果
これでは、新しい血がいかない。
ので、(1)の効力でまずは、血がでるのを止める。
そして、冷やすと、少ない酸素の量で新陳代謝がしやすくなるようだ。
新しい血が行く量が仮に少なくとも、体の再生がしやすくなる。
(3)痛みを麻痺させる効果
そのことが「痛い→筋肉硬直→痛み→筋肉硬直」というループを防ぐ
こんなところでどうでしょうか?
私はわかった気になりましたが、みなさんはなりましたでしょうか?
自分の体の調子がわるくなるというのもまた、勉強だと理解できた今日でした。
読んでいただきありがとうございました。
興味はあるんだけど
- 失敗したくないから一度試したい
- 家に人を呼ぶってのがイメージできないから、お試ししたい
- 施術の圧加減などが自分に合うか、リスクを減らして試してみたい
という、新規の方向けに、40分6,000円でお試し施術しています。
(通常30分6000円にお試し用で10分追加プレゼント)
期間限定なので、お早めに。
下記お試し専用Lineより、ご連絡くださいませ。
Lineに登録すると、他にも事前予約割引や、お得なスタンプカードも得られます。
ご登録して損はありませんよ。
詳しい情報として下記もご参考になさってください。
こんな時にもお役に立てます。
- 【メンタル疲れ】愚痴を聞いてくれる整体
- 【夜遅く受けたい】夜遅く(深夜)でも受けられる月一出張整体!
- 【家に来て欲しい】家から出るのがめんどくさい
- 【気分が落ち込んでいる】メンタルがネガティブになったら整体をうけるべし
- 【肩が疲れた】重いバックを長時間肩にかけたので肩こりが
- 【足のむくみ】リモートワークで歩かなくて足を動かしてないのでだるい
- 【介護疲れ】介護職で腕が疲れた
- 【考え過ぎ疲れ】勉強しすぎて頭が疲れた
- 【PC使いすぎ疲れ】タイピングのしすぎで指が疲れた
- 【仕事しすぎ疲れ】残業が多く姿勢が悪くなってきた
- 【コロナ禍疲れ】マスクしすぎてなんか少し息苦しい
- 【コロナ禍疲れ】ヘッドホンやマスクで耳が疲れた
メニュー
サブメニュー